【介護保険サービス一覧】種類や内容、利用料をわかりやすく解説

介護が必要になったとき、「どのようなサービスがあるのか」「何から始めればいいのか」と戸惑う方は少なくありません。公的介護保険制度では、訪問介護や通所介護、施設入所など、状況や希望に応じたさまざまな介護保険サービスを利用できます。
この記事では、介護保険サービスを一覧にしてわかりやすく解説します。利用料や利用時の流れに加え、注意点にもふれていますので、ぜひ参考にしてください。
介護保険サービスとは
介護保険サービスとは、公的介護保険制度を利用して受けられる介護サービスのことです。高齢者の介護を家族だけに任せるのではなく、社会全体で支え、自立した日常生活を送れるよう支援する社会保険制度として設けられています。
65歳以上は「第1号被保険者」、40歳から64歳までは「第2号被保険者」と区分され、第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けた場合に介護サービスを受けられます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた場合に限り、介護サービスを受けることが可能です。
要介護度は「要支援1・2」「要介護1~5」の計7段階に分かれており、認定の度合いによって受けられるサービスの種類や利用限度額が決まります。
介護保険サービス一覧
介護保険サービスは、多様な種類が用意されており、介護を必要とする方の状態や生活環境に応じて、選択できます。大きく分けると「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」などがあり、それぞれに該当するサービスが細かく分類されています。
介護保険サービスの種類と利用環境は下記のとおりです。
■介護保険サービス一覧
| サービス名 | サービスの種類 | 利用環境 |
|---|---|---|
| 居宅サービス (自宅で生活を続けるための介護サービス) | 訪問介護 | 自宅での支援(訪問) |
| 訪問入浴介護 | ||
| 訪問看護 | ||
| 訪問リハビリテーション | ||
| 居宅療養管理指導 | ||
| 通所介護 | 施設等への通所 | |
| 通所リハビリテーション | ||
| 短期入所生活介護 | 短期間の宿泊 | |
| 短期入所療養介護 | ||
| 特定施設入居者生活介護 | 施設等での生活 | |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具の使用 | |
| 特定福祉用具販売 | ||
| 地域密着型サービス (市区町村で提供される小規模介護サービス) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 自宅での支援(訪問) |
| 夜間対応型訪問介護 | ||
| 地域密着型通所介護 | 施設等への通所 | |
| 療養通所介護 | ||
| 認知症対応型通所介護 | ||
| 認知症対応型共同生活介護 | 施設等での生活 | |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
| 小規模多機能型居宅介護 | 訪問・通所・宿泊の組み合わせ | |
| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | ||
| 居宅介護支援 (ケアプラン作成とサービス調整) | - | 介護の相談・ケアプラン作成 |
| 施設サービス (介護保険施設に入所して介護や医療的支援を受けるサービス) | 介護福祉施設サービス | 施設等での生活 |
| 介護保健施設サービス | ||
| 介護医療院サービス | ||
介護予防サービス (要介護状態を防ぐための支援サービス) | 介護予防訪問入浴介護 | 自宅での支援(訪問) |
| 介護予防訪問看護 | ||
| 介護予防訪問リハビリテーション | ||
| 介護予防居宅療養管理指導 | ||
| 介護予防通所リハビリテーション | 施設等への通所 | |
| 介護予防短期入所生活介護 | 短期間の宿泊 | |
| 介護予防短期入所療養介護 | ||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 施設等での生活 | |
| 介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具の使用 | |
| 特定介護予防福祉用具販売 | ||
地域密着型介護予防サービス (市区町村で提供される、要介護状態を防ぐための支援サービス) | 介護予防認知症対応型通所介護 | 施設等への通所 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 訪問・通所・宿泊の組み合わせ | |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 施設等での生活 | |
介護予防支援 (ケアプラン作成とサービス調整) | - | 介護の相談・ケアプラン作成 |
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 -」新規ウィンドウを開きますをもとに当社にて作成
次に、一覧で紹介した各サービスについて、見ていきましょう。
居宅サービス
居宅サービスとは、介護を必要とする方が自宅での生活を継続できるよう支援するサービスのことです。訪問や通所、短期宿泊などのサービスがあり、居宅で生活を続けたいと考える高齢者にとって、居宅サービスは身近で利用しやすい支援手段といえます。
たとえば、身体の不自由により買い物や入浴が困難な場合には「訪問介護」、外出が難しい高齢者に対しては「訪問リハビリテーション」、家族の介護負担を軽減したいときには「短期入所生活介護」が活用できます。
なお、居宅サービスは必ずしも、自宅にいる方向けのサービスを意味するわけではありません。「利用者が生活の拠点としている場所」が該当するため、軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含まれます。そのため、「特定施設入居者生活介護」のように、有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している方に向けた支援も、居宅サービスに含まれます。
居宅サービスは原則として要介護の方が対象ですが、サービスによって利用条件が異なるため、事前に確認しましょう。
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、利用者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、市区町村単位で提供される小規模な介護サービスのことです。家庭的な雰囲気の中で、少人数に対してきめ細かな支援を受けられるのが特徴です。
地域密着型サービスは、原則としてサービス事業所の所在する市区町村の住民のみが対象であり、地域とのつながりを重視しています。たとえば、「小規模多機能型居宅介護」では、訪問・通所・宿泊の3つのサービスが一体的に提供されており、日々の状況に応じた利用が可能です。また、「認知症対応型通所介護」では、専門のスタッフによる認知症ケアを家庭的な環境の中で受けられます。
地域密着型サービスは原則、要介護の方が対象ですが、細かな条件はサービスによって異なります。
居宅介護支援(ケアマネジメント)
居宅介護支援とは、介護サービスを適切に利用するために必要なケアプランの作成や、サービス事業者との連絡・調整を行う支援のことです。ケアプランの作成や調整は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が担当します。
介護保険サービスは種類が多く、要介護度や家庭の状況に応じて必要なサービスを選んで利用することが大切です。ケアマネジャーが調整役となり、本人や家族の意向を反映したケアプランを作成することで、無理のない介護生活をサポートします。
なお、居宅介護支援は、要介護の方が対象です。
施設サービス(介護保険施設)
施設サービスとは、施設に入所して、生活支援や在宅復帰支援、長期療養支援を受けるサービスのことです。利用者の心身の状態や目的に応じて、「介護福祉施設サービス」「介護保健施設サービス」「介護医療院サービス」のいずれかで、日常生活のケアや医療的な支援を受けながら生活します。
「介護福祉施設サービス」では、常に介護が必要な高齢者が生活全般の支援を受けられ、「介護保険施設サービス」では、リハビリ等で在宅復帰を目指します。「介護医療院サービス」では、慢性的な病気を抱える高齢者は医療と介護の両方を受けることが可能です。原則として、要介護の方が対象ですが、細かな条件はサービスによって異なります。
介護予防サービス
介護予防サービスとは、要支援状態の方ができる限り自立した生活を維持できるように支援するサービスのことです。身体機能や生活能力の維持・向上を目的としたリハビリのほか、運動指導、栄養管理、生活支援など、日常生活の自立を促す多様なサービスが提供されています。
たとえば、「介護予防訪問看護」では、看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や医療処置、療養上の世話などを行います。「介護予防通所リハビリテーション」では、軽度の体力低下を防ぐための機能訓練が可能です。
原則として要支援の方が対象ですが、細かな条件はサービスによって異なります。
地域密着型介護予防サービス
地域密着型介護予防サービスとは、要支援状態の方が地域での生活を継続できるように支援する、小規模で柔軟性の高いサービスのことです。少人数制で提供され、利用者の生活リズムや性格に合わせた支援が行われます。地域とのつながりを大切にしているため、孤立の防止や心のケアにも寄与する点が特徴です。
「介護予防小規模多機能型居宅介護」では、訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービスが提供され、「介護予防認知症対応型通所介護」では、認知症の進行を遅らせるための活動が行われます。サービスを提供する事業所のある市区町村に住んでいることが利用の条件です。原則として、要支援の方が対象ですが、細かな条件はサービスによって異なります。
介護予防支援
介護予防支援とは、要支援状態の方に対して、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が中心となってケアプラン(介護予防サービス・支援計画書)を作成するサービスのことです。高齢者一人ひとりの心身の状態に応じた適切な介護予防サービスを選定し、利用できるようにサポートします。また、ケアプラン作成後も継続的にモニタリングし、状態の変化に応じて調整を行います。
介護保険サービスにかかる利用料
介護保険サービスの利用時は、原則としてかかった費用の一部を自己負担しなければなりません。サービスにかかった費用の1割、もしくは一定以上所得者の場合は2割または3割負担となります。限度額を超えた分は、全額自己負担となるため注意が必要です。また、介護保険施設に入所する場合の「居住費」「食費」「日常生活費」や、通所介護での「食費」「おむつ代」などの費用は、介護保険の対象外であるため、実費負担(全額自己負担)です。
居宅サービスを利用する場合は、要介護度ごとに1か月あたりの利用限度額が設定されています。「区分支給限度基準額」といい、限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。
■居宅サービスの1か月あたりの利用限度額
| 要介護度 | 限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 5万320円 |
| 要支援2 | 10万5310円 |
| 要介護1 | 16万7650円 |
| 要介護2 | 19万7050円 |
| 要介護3 | 27万480円 |
| 要介護4 | 30万9380円 |
| 要介護5 | 36万2170円 |
出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」新規ウィンドウを開きます
なお、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」などの施設サービスについては、個室か多床室(相部屋)かなどの住環境によって自己負担額が変わるため、事前に詳細を確認しましょう。
介護保険サービスの利用時の流れ
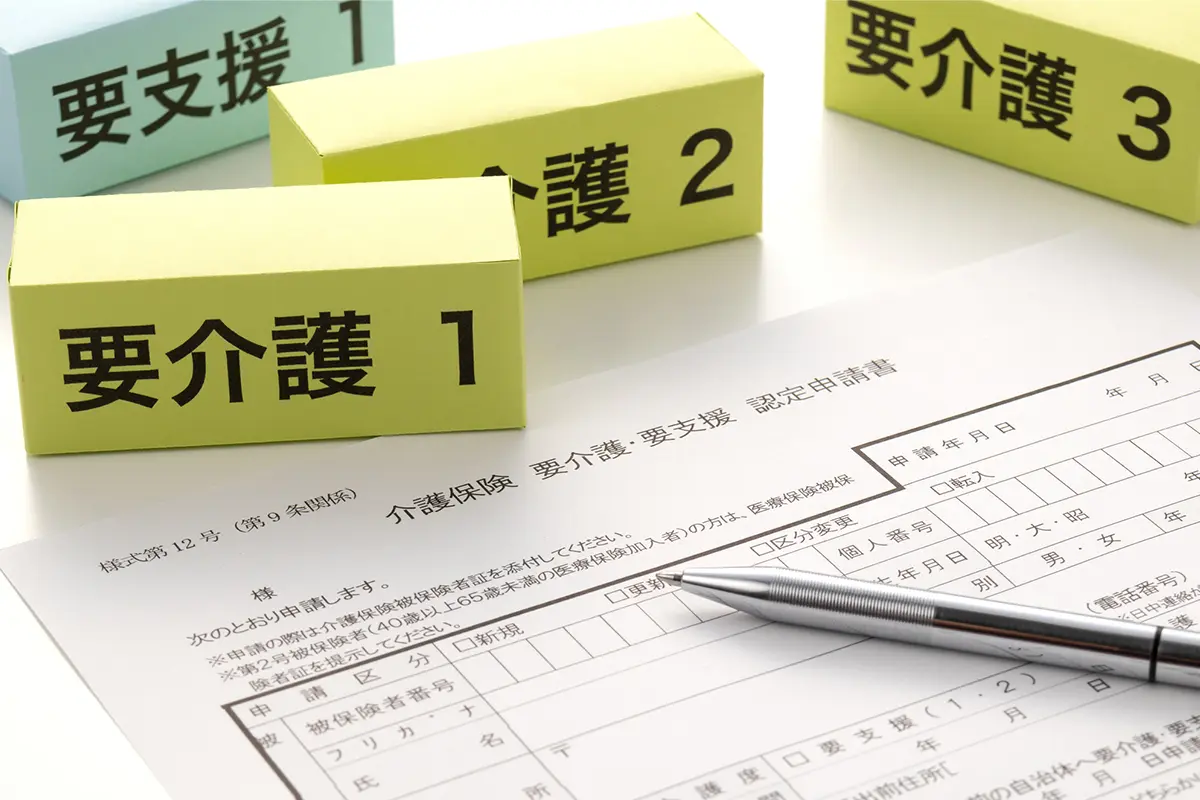
介護保険サービスを利用するには、まず要介護(または要支援)の認定を受ける必要があります。介護保険サービスの利用時の基本的な流れは、下記のとおりです。
- 1市区町村の窓口またはオンラインで要介護(要支援)認定を申請
- 2認定調査・主治医による意見書作成
- 3審査・判定
- 4認定
- 5ケアプランの作成
- 6サービスの利用を開始
スムーズに進めるためには、ケアマネジャーのサポートを受けながら進行するのがおすすめです。
介護保険サービスを利用する際の注意点
介護保険サービスは高齢者や家族を支える心強い制度ですが、利用にあたってはいくつか注意するべきことがあります。ここでは、介護保険サービスを利用するうえで知っておきたい注意点を紹介します。
家族と相談のうえ介護保険サービスを利用する
介護は利用者だけでなく家族の生活にも影響します。そのため、介護保険サービスを利用する前に家族で話し合うことが大切です。在宅介護または施設入所、どちらを選ぶかなど、利用者の希望と家族の状況を踏まえて、サービスを利用しましょう。
介護保険対象外のサービスがある
介護保険の対象外となるサービスがある点にも注意しなければなりません。たとえば、訪問介護では、ヘルパーが提供できるサービスの内容は厳格に決められています。利用者以外を対象とした家事や、買い物と通院以外の外出援助などは提供できません。このようなサービスを利用したい場合は、自費でのサービスや自治体が提供する支援制度を組み合わせることで、より安心した生活を送ることができます。
介護保険サービスを正しく理解し、安心してサービスを受けよう
介護保険サービスは、要支援・要介護の状態になっても、自分らしい生活を続けるための支えとなる制度です。サービスの種類は多岐にわたり、利用者の状況や希望に応じて組み合わせられます。家族と相談を重ねながら、必要なタイミングで適切な支援を受けられるようにすることが、将来の安心につながります。そのためには、サービスの概要や費用などについて理解を深めておくことが大切です。また、介護保険サービスの利用時には、ケアマネジャーや地域包括支援センター・居宅介護支援事業所のアドバイスも受けながら、適切なサービスを利用しましょう。

介護福祉士
中谷 ミホ さん
介護福祉士、ケアマネジャー、社会福祉士、保育士。福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在は介護業界での経験を活かし、介護に関わる記事を多く執筆。介護・福祉関連書籍の監修も手掛けている。
- ※本ページ上の保険の説明は、一般的と考えられる内容を掲載しています。個別の保険商品については、各保険会社の公式サイトをご確認ください。
- ※掲載している内容は、2025年7月29日時点のものです。
- ※ページ内のコンテンツの転載を禁止します。
