大切なペットとの“いきいき”とした暮らしのために
犬猫お役立ち情報
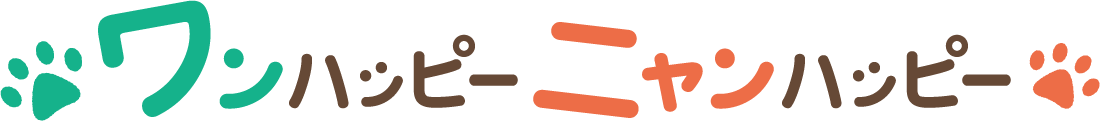
犬の生活
犬のワクチンの種類・料金は?子犬・成犬の接種スケジュールを紹介

目次
「子犬の散歩デビューはワクチン接種を済ませてからと聞いたけれど、どんなワクチンが必要なの?」「愛犬のワクチンの接種スケジュールが把握できなくて困っている」など、犬のワクチンについて疑問がある方もいるでしょう。
本記事では、犬のワクチンの種類や料金、接種スケジュールについて解説します。
犬のワクチン種類別の料金表
犬のワクチンには様々な種類があります。
混合ワクチンに含まれるワクチンの種類例と狂犬病ワクチンについて、下記にまとめています。
| 名称 | 予防対象の病気 | 参考料金(1回分) |
|---|---|---|
| 2種混合ワクチン | ジステンパーとパルボウイルス感染症 | 3千~5千円 |
| 3種混合ワクチン | ジステンパーと伝染性肝炎、アデノウイルス2型感染症 | 3千~5千円 |
| 4種混合ワクチン | 上記3種とパラインフルエンザ | 5千~6千円 |
| 5種混合ワクチン | 上記4種とパルボウイルス感染症 | 5千~7千円 |
| 6種混合ワクチン | 上記5種とコロナウイルス感染症 | 5千~8千円 |
| 8種混合ワクチン | 上記6種とレプトスピラ感染症2種 | 6千~9千円 |
| 10種混合ワクチン | 上記6種とレプトスピラ感染症4種 | 8千~1万2千円 |
| 11種混合ワクチン | 上記6種とレプトスピラ感染症5種 | 8千~1万2千円 |
| 狂犬病ワクチン | 狂犬病 | 3千~4千円 |
内容や費用は一例なので、動物病院で確認しましょう。
ワクチン接種によって防げる病気の詳細
法律で年1回の接種が義務付けられているのが狂犬病ワクチンです。その他に、すべての犬が接種すべきと考えられている「コアワクチン」と、任意で接種する「ノンコアワクチン」があります。主なものは下記の通りです。なお、義務化されている狂犬病ワクチンはコアワクチンの1つです。
| ワクチンの種類 | 対象の病気 |
|---|---|
| コアワクチン | 狂犬病・ジステンパー・伝染性肝炎・アデノウイルス2型感染症・パルボウイルス感染症 |
| ノンコアワクチン | コロナウイルス感染症・パラインフルエンザ・レプトスピラ感染症 |
それぞれの病気について紹介します。
狂犬病
狂犬病は発症すると致死率ほぼ100%の恐ろしい感染症です。人を含めたすべての哺乳類に感染する恐れのある人畜共通感染症で、生後91日以上の子犬を含むすべての飼い犬に対して、年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。
ジステンパー
ジステンパーは、ワクチン未接種の場合、発熱などの急激な症状が見られ、発症すると死亡率が高い病気です。ジステンパーに感染した犬のよだれや鼻水、排泄物などの飛沫から空気感染します。
伝染性肝炎
伝染性肝炎は、重篤化すると肝臓や肺などが冒され、炎症を起こすものです。肝炎は症状に気がつきにくく、ワクチン未接種の子犬の場合、高熱と虚脱状態から急に症状が悪くなり死に至ることもあります。
アデノウイルス2型感染症
アデノウイルス2型感染症は、ケンネルコフ(犬伝染性気管支炎)の原因の一つであり、乾いた咳をするのが特徴です。感染力が強く混合感染により重篤化します。アデノウイルスのワクチンを接種することで、伝染性肝炎とアデノウイルス2型感染症の両方を予防することができます。
パルボウイルス感染症
パルボウイルス感染症は、子犬やシニア犬で感染すると死亡する恐れもある病気です。嘔吐や激しい下痢、ケチャップのような血便を起こすことがあります。パルボウイルスは環境中での生存力も強く、感染力の高いウイルスです。
コロナウイルス感染症
コロナウイルス感染症は、ウイルスを保有している犬の糞から感染する病気です。症状は比較的軽度であることが多いですが、子犬の場合は症状が強く、ほかのウイルス感染を併発すると脱水を起こすなど、命の危険を伴うことがあります。
※ここで指しているコロナウイルス感染症は、新型コロナウイルス(COVID-19)とは異なります。
パラインフルエンザ
パラインフルエンザだけの感染では、症状がわからないこともありますが、ほかのウイルスや細菌感染を併発するとケンネルコフの原因になることがあります。
レプトスピラ感染症
レプトスピラ感染症は、ネズミなどのげっ歯類が高確率で保有しているウイルス由来の感染症です。ウイルスを保有しているげっ歯類の排泄物によって汚染された土壌・水などから感染し、症状は軽いものから、腎炎、肝炎など重症になることもあります。
都市部でも発症例が多数あることに加え、人畜共通感染症であるため、注意が必要です。住んでいる地域の発生状況などに関しては、獣医師に確認しましょう。
子犬・成犬のワクチン接種スケジュール

ワクチン接種のスケジュールは、子犬か成犬かで異なるため、分けて解説します。
子犬の散歩デビューの時期についても触れますので参考にしてください。
子犬のワクチン接種スケジュール
子犬を家族に迎えたら、動物病院で健康診断をしてもらうとよいでしょう。その際に、現在のワクチン接種状況を伝え、今後のワクチンのスケジュールについて獣医師とプログラムを組み、今後の見通しを立てましょう。
一般的なワクチン接種スケジュールは次の通りです。
一般的に、子犬に母犬から譲り受けた抗体が残っている場合を考慮し、3回の混合ワクチン接種が推奨されています。
母犬の初乳を通して、子犬に抗体を譲り受けることを移行抗体と言います。この抗体は成長と共に消えていきます。一方、抗体が残っている時期にワクチンを打った場合、移行抗体が邪魔をして、子犬自身は充分に免疫をつけることができません。
特に、子犬の場合は一度にたくさんの種類のワクチンを体内に入れると副反応のリスクが高まります。愛犬にどのワクチンを接種するかは、獣医師と相談して決めましょう。
子犬の散歩はワクチン何回目から?
子犬の散歩デビューは、ワクチン2回目接種後であればよいとされる場合もあります。しかし、感染症にかかる可能性は否定できません。
安全を期すには、3回目のワクチン接種後2週間を目安としましょう。
なお、住んでいる地域の伝染病などの発生状況にも左右されるため、いつから散歩が可能かは、必ずかかりつけの獣医師に相談しましょう。
成犬のワクチン接種スケジュール
成犬のワクチン接種頻度は基本的に年に1回となっています。
スケジュールの都合上、混合ワクチンを先に接種した場合は、狂犬病ワクチンの接種を行うまで1か月ほど間隔をあけましょう。
なお、コアワクチンについては世界的に3年に1回の接種が推奨されており、世界小動物獣医師会(WSAVA)によるガイドライン で公表されています。また弱毒性(MLV)のコアワクチン接種に副反応のあった犬については、3年以上の間隔をあけて接種を行ってもよいとされているのが現状です。
犬のワクチン接種は地域ごとの伝染病などの発生状況にも左右されます。獣医師と相談して、スケジュールを決めるとよいでしょう。
犬にワクチンが必要な理由

子犬に限らず愛犬が恐ろしい病気にかからないためにも、またほかの犬への感染症の蔓延を防ぐためにも、犬へのワクチンは必要です。ワクチン接種が必要な理由を詳しく見ていきましょう。
子犬のうちにワクチンを接種すべき理由
生後1か月半~3か月頃の子犬は、初乳からの免疫が徐々に減っていくため、いろいろな感染症にかかるリスクが出てきます。感染予防をするために子犬へのワクチン接種が必要となります。
成犬が定期的にワクチンを接種し直すべき理由
ワクチンの効果は時間が経つと薄れてしまいます。犬に感染する可能性のある病気が蔓延することを防ぐためにも、ワクチン接種は欠かせません。
また、ペットホテルやドッグランなど、施設によっては、混合ワクチンの毎年接種を義務付けているところもあるため、利用を予定している場合は事前に確認しておくと安心です。病院からもらうワクチン証明書をなくさないようしっかり保管しておきましょう。
犬のワクチン接種時に注意したいことと副反応について
ワクチン接種には副反応のリスクがあります。ワクチン接種後に体調を崩す犬もいるので、当日は安静にし、愛犬の様子をしっかり観察しておきましょう。
ここではワクチン接種の際に注意すべきことを紹介します。
ワクチン接種前に注意すること
ワクチン接種前のシャンプーなどは、犬の疲労やストレスにつながるので控えましょう。
また、直近で治療を受けた、1か月以内にほかのワクチン接種を行っているといった場合は必ず獣医師に伝えましょう。
人と同様、健康面で問題がない場合にワクチン接種を受けることが大切です。
ワクチン接種当日
ワクチン接種当日は、愛犬が元気であるかをチェックしてから接種を行いましょう。接種後は、顔が腫れる、体が赤くなる、嘔吐や下痢、発熱、元気がない、フラフラするといった全身的な副反応が出る可能性もあります。当日は激しい運動をさせないようにしましょう。
また、当日、初めてのフードやおかしなどを与えて体調が悪くなった場合、ワクチンの副反応か食べ物の影響なのか判断がつきません。ワクチン接種当日は初めての食べ物は与えないようにしましょう。
ワクチン接種から2〜3日後
ワクチンを打って数日は、シャンプーや激しい運動は控えましょう。2〜3日経ってから、具合が悪くなる、食欲がなくなる、注射した部分が腫れるといった副反応が見られる場合もあります。接種後2~3日は、ふだん以上に愛犬の体調を見守りましょう。
犬の様々な病気の予防につながるワクチンはしっかり打とう
狂犬病ワクチンは法律により年1回の接種義務があります。コアワクチンは3年に1度受けさせることが推奨されています。また、定期的なワクチンの接種が感染症の予防につながります。
ペットホテルやドッグランなど、施設によっては年に1度のワクチン接種を受けていないと利用できない場合もあることを把握しておきましょう。
子犬も成犬も、獣医師と相談のうえ、必要な時期にしっかりワクチンを接種して様々な病気を予防することが大切です。
- ※掲載している内容は、2024年7月18日時点のものです。
- ※ページ内のコンテンツの転載を禁止します。









